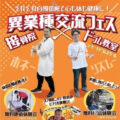今回は、奈良県奈良市にある奈良町にぎわいの家について紹介します。
施設の様子をまとめたのでご覧になって下さい。
Contents
1. 施設情報
1) 奈良町にぎわいの家
①紹介
・文化・生活体験施設(奈良県奈良市)
・ならまちの中にある施設
・大正時代の文化や生活を体験できる施設
・1917年築(築約100年)の町家
②コンセプト
・テーマは二十四節気で季節を感じる町家
・住まいの知恵や伝統の技など日本の暮らしを伝える町家
・空間から生まれる文化や生活を体験できる町家
③設立
・2015年4月
④入場料
・無料
⑤駐車場
×なし(公共交通機関をご利用下さい)
・車でお越しの方はお近くのパーキングに駐車してからお越し下さい。
(A) アクセス
〒630-8333
奈良県奈良市中新屋町5
◇最寄り駅
・近鉄 奈良線 奈良駅 東改札口 (徒歩: 約15分)
「奈良公園の最寄り駅」
・JR 関西本線 奈良駅 東改札口(徒歩: 約20分)
「なら100年会館の最寄り駅」
2. 最寄りの駅からの道順
・駅から施設への行き方: 1通り
1) 電車での行き方1
・近鉄 奈良線 奈良駅で降ります。
(徒歩: 約15分)
a) 近鉄 奈良線 [大阪難波] 駅
(JR、地下鉄、南海から乗換)→ 急行 約40分
a’) 近鉄 奈良線 [大和西大寺] 駅 → 急行・普通 約5分
↓
①東改札口より2番出口を出てから、行基広場に行って下さい。
そこから、右に曲がって下さい。

↓
②ひがしむき商店街を通って下さい。

↓
③ひがしむき商店街・出口の横断歩道を渡って、左に曲がって下さい。

↓
④もちいど商店街を通って下さい。

↓
⑤もちいど商店街の角を左に曲がって下さい。

↓
⑥猿田彦神社の角を右に曲がって下さい。

↓
⑦奈良町情報館の横断歩道を渡って、直進して下さい。

↓
⑧奈良町にぎわいの家に到着 → 1階・入口から入って下さい。
中に入るときは靴を脱いで下さい。

3-1. 施設の紹介(1階)
1) 玄関
・季節に合わせて飾り付けをされています。

2) 座敷1
・緑色系の畳で自然を感じて癒されます。
・イベント開催: 文化体験関連

3) 座敷2
・黄色系の畳でぬくもりを感じて過ごせます。
・イベント開催: 文化体験関連

4) 座敷3
・茶色系の畳で奥ゆかしさ感じて落ち着けます。
・イベント開催: 文化体験関連

5) 茶室
・畳があって少し暗めだが、庭を眺めると晴れやかな気持ちになれます。
・イベント開催: お茶関連

6) 離れ
・畳があり、中庭や裏庭を眺めながらくつろげます。
・イベント開催: 文化体験関連

7) 通り庭
・かまど、たんす、洗面所があり、台所としての役割を果たします。
・イベント開催: 食体験関連

8) 庭園
・緑色の豊かな木や石を眺めて過ごせます。

9) 伽藍石(がらんいし)
・玄関先にあって、大きな石に迫力を感じます。

10) 階段
・2階へ通じる階段で、隠れ部屋へ行くことが可能です。

3-2. 施設の紹介(2階)
1) 店の間
・天井が低く、隠れ部屋のような感じを受けられます。

4. 設備
1) かまど1
・複数のかまどが連なっています。
・使用イベント: 食関連

2) かまど2
・単数のかまどの横に風情ある木材のたんすがあります。
・使用イベント: 食関連

3) 蓄音機
・レコードを置いてかけると音楽を聴くことでき、音や機械を通して
風情を感じられます。
・使用イベント: 文化関連
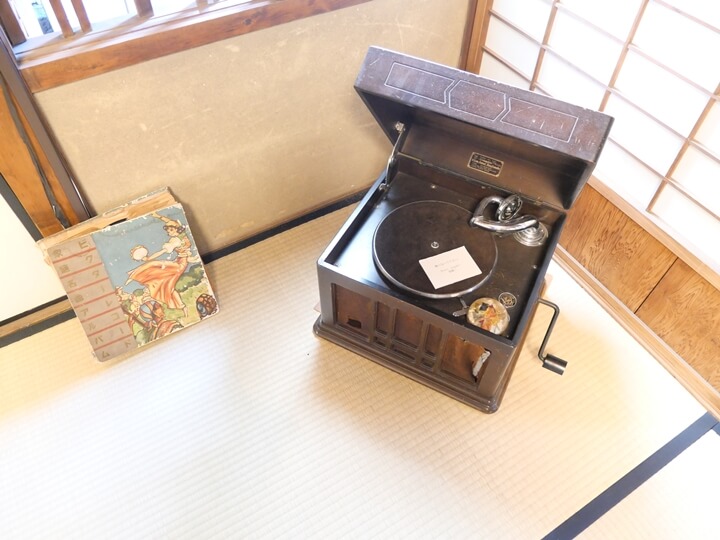
5. 文化体験/気軽に月イチ体験
★月に1回程度開催される文化体験イベント
X) 説明
①開催日
・月1回程度(14:00~15:30ごろ)
☆講師の方や会場の都合で不定期に開催されるので、
奈良町にぎわいの家のFacebookで日程や内容の確認をお願いします。
↓
□Facebook: 奈良町にぎわいの家
②道具
・講師の先生や施設のスタッフの方に用意して頂けます。
(参加者:×道具の用意は不要)
③参加方法
×事前申込: 不要
・直接、会場にお越しになって下さい。
・参加費: 無料
1) 書道体験
①内容
・毛筆と墨を使って、半紙に文字を書く体験
2) 水墨画体験
①内容
・毛筆と墨を使って、絵を描く体験
3) 絵手紙体験
①内容
・毛筆と墨を使って、はがきに絵と文字を描く体験
4) 茶の湯遊び
・茶筅(ちゃせん)と茶碗を使って、抹茶を立てる体験
5) 蓄音機体験
・テーマにセレクトしたSPレコードを置いて、蓄音機を操作して
音楽を楽しむ体験
6) 町家ばなし
・大正時代の町の暮らしなどを講師の方に話して頂き、参加者には
聞いて学んで頂く体験
6. 食体験
★不定期に開催される体験イベント
X) 説明
①準備物
・詳しい日程や内容は奈良町にぎわいの家のFacebookで確認をお願いします。
↓
□Facebook: 奈良町にぎわいの家
①開催日
☆講師の方や会場の都合で不定期に開催されます。
②準備物
☆基本、講師の先生や施設のスタッフの方に用意して頂けます。
(イベントによって用意して頂く必要があります)
③参加方法
☆事前申込の方法はイベントによって異なります。
④参加費
☆参加費(無料、有料)はイベントによって異なります。
1) かまど体験
①内容
・施設内にあるかまどを使って、ご飯を炊く体験ができます。
・にぎわいの裏の畑で採れた野菜で調理されます。
(カレーライス、みそ汁、漬物、おひたしなど)
・体験後は参加者と講師の方で食事を通して交流も行えます。
2) みんなで餅つき大会
①内容
・施設内にある石臼と杵を使って、餅つきができます。
・ついた餅はデザートにして召し上がれます。
(ぜんざいなど)
★上記以外にも多数の講座を用意されています。
7. 文化講座
★不定期に開催される講座イベント
X) 説明
①準備物
・詳しい日程や内容は奈良町にぎわいの家のFacebookで確認をお願いします。
↓
□Facebook: 奈良町にぎわいの家
①開催日
☆講師の方や会場の都合で不定期に開催されます。
②準備物
☆基本、講師の先生や施設のスタッフの方に用意して頂けます。
(イベントによって用意して頂く必要があります)
③参加方法
☆事前申込の方法はイベントによって異なります。
④参加費
☆参加費(無料、有料)はイベントによって異なります。
1) クイズで学ぶ二十四節気と俳句講座
①内容
・クイズ形式で二十四節気と季節の俳句を学べます。
2) やさしい短歌
①内容
・季節の名歌を詠んで短歌を作ります。その後、講師の方に添削して頂き、
発表して頂けます。
3) こまで遊ぼう
①内容
・講師の方にこまの回し方を指導して頂き、実際にこまを回して遊べます。
★上記以外にも多数の講座を用意されています。
8. 企画展
X) 説明
①開催日
☆不定期で開催されるので、奈良町にぎわいの家のFacebookで日程や内容の
確認をお願いします
↓
□Facebook: 奈良町にぎわいの家
②参加方法
×事前申込: 不要
・直接、会場にお越しになって下さい。
・参加費: 無料
1) 展示企画
・町家に活かして季節や行事に合わせた展示がされています。
①屏風飾り 「テーマ: 二十四節気」
・奈良町にぎわいの家オリジナルマーク
9. 二十四節気
#二十四節気…
・二十四節気とは、太陽の黄道(こうどう)上の動きを視黄経の
15度ごとに24等分して約15日ごとに分けた季節のこと。
a. 全体: 春夏秋冬の4つの季節に分ける
b. 部分: それぞれを6つに分ける
「節気(せっき)と中気(ちゅうき)を交互に配置する」
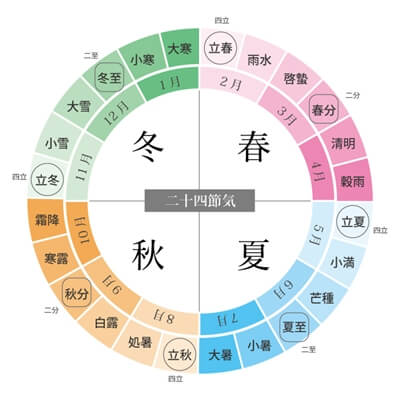
1) 春
(A) 2月
①立春(りっしゅん): 2/3~2/17
・旧暦ではこの日が一年の初め
②雨水(うすい): 2/18~3/4
・雪が雨に、氷が水になり、草木が芽生えます
・農耕の準備を始める目安である
(B) 3月
①啓蟄(けいちつ): 3/5~3/19
・日差しも徐々に暖かくなり、冬眠していた虫が土中から
出てくる頃で春の気配が近づきます。
②春分(しゅんぶん): 3/20~4/3
・昼と夜の長さがほぼ同じになる日
・春のお彼岸はこの時期です。
・寒さもだいぶ和らいできます。
(C) 4月
①清明(せいめい): 4/4~4/19
・万物が若返り、清々しく明るく美しいとされる季節です。
・お花見のシーズンでもあります。
②穀雨(こくう): 4/20~5/4
・田植えの準備をする目安とされます。
・穀雨の時期が終わるころが茶摘みのシーズン
2) 夏
(A) 5月
①立夏(りっか): 5/5~5/20
・暦の上ではこの日から夏の始まりです。
・新緑の季節で帰るが泣き出すのもこの頃からです。
②小満(しょうまん): 5/21~6/4
・麦の穂が育ち、山野の草木が実をつけ始める
・だんだんと暑くなってくる季節
(B) 6月
①芒種(ぼうしゅ): 6/5~6/20
・雨が多くなり梅雨の気配が近づいてきます。
・蛍が現れ始めるのもこの季節
②夏至(げし): 6/21~7/6
・1年で最も昼間が長く夜が短い日です。
・雨の多い梅雨の時期で、肌寒い日もあります。
(C) 7月
①小暑(しょうしょ): 7/7~7/21
・七夕の季節
・梅雨が明け、強い日差しとともに気温が一気に上昇します。
②大暑(だいしょ): 7/21~8/6
・気温はさらに上がり、本格的な夏の到来です。
大暑に合わせて打ち水のイベントを行うこと
3) 秋
(A) 8月
①立秋(りっしゅう): 8/7~8/22
・まだまだ圧阿賀厳しいです。
・この日から暑中ではなく残暑見舞いになります。
②処暑(しょしょ): 8/23~9/6
・厳しい暑さのピークを越え、厚さが和らぐ季節。
・台風シーズンでもあります。
(B) 9月
①白露(はくろ): 9/7~9/22
・草の葉に白い露が結ぶという意味
・日中は暑さが残りますが朝夕は涼しくなりはじめます。
②秋分(しゅうぶん): 9/23~10/7
・秋分と同様、昼夜の長さがほぼ同じになる日である。
・秋のお彼岸の時期。暑さも和らぎ始めます。
(C) 10月
①寒露(かんろ): 10/8~10/22
・秋の長雨が終わり、秋晴れの日が多くなります。
・収穫シーズンであり、本格的な秋の始まりです。
②霜降(しもふり): 10/23~11/6
・秋の一段と深まり、山は紅葉で彩られます。
・朝晩が冷え込み始め、冬の気配が近づきます。
4) 冬
(A) 11月
①立冬(りっとう): 11/7~11/21
・暦の上ではこの日から冬の始まりとなります。
・木枯らしや初霜の便りも届き始めます。
②小雪(しょうせつ): 11/20~12/7
・日差しが弱くなり、紅葉が散り始めます。
・冷え込みが厳しくなり冬の準備を始めます。
(B) 12月
①大雪(だいせつ): 12/8~12/21
・山岳だけでなく、平野にも雪が降るとされる。
・全国的に冬の気配が強まってきます。
②冬至(とうじ): 12/22~1/4
・夏至と反対に、夜が最も長く昼が短い日とされます。
・魔除けにかぼちゃや小豆粥を食べる風習もある
(C) 1月
①小寒(しょうかん): 1/5~1/19
・「寒の入り」と言われ冬本番に入ります。
・この日から寒中見舞いを出し始めます。
②大寒(だいかん): 1/20~2/2
・一年最も寒い時期
・寒気を利用した食べ物を仕込むのに最も良い時期
10. まとめ
良町にぎわいの家は、大正時代の町家を活かした施設です。
多種類の大正時代の文化や生活を体験でき、道具は講師の先生や施設のスタッフに
用意して頂けるので、参加者は気軽に参加できます。また、丁寧に指導して頂けるので
安心して楽しめます。さらに、町家の温もりを感じることができて心が癒されます。
ならまちにお越しになったときには施設を訪問してみて下さい。
今後も施設やイベントの活性化を願い、奈良町にぎわいの家の発展をお祈り申し上げます。